MOVED INTO HERE : 2006.01.01

2024/01/24 15:26 ボードゲーム
テラミスティカ攻略1 基本編
2023/11/10 17:07 ゲーム・論考
FrontPage
2022/08/28 09:31
『縦帝国』の広告を廃止した話
2022/08/28 09:28 ゲーム制作
Android用ゲーム『縦帝国』を作りました
2022/08/05 05:08 ゲーム制作
ボードゲームはコミュニケーションツールではない
2020/09/21 13:18 ゲーム・論考
URLが変わりました
2018/06/02 11:48 日記
マップ不要論と、いやそうでもないかもという話
2016/12/23 14:06 ゲーム・論考
サンファン
ボードゲーム
alea
Andreas Seyfarth
2-4人(まあ何人でも)
30分
プエルトリコの浮浪者街がSunJuanで、ずっと「サンジュアン」と読んでいたわけだが、考えてみれば、あっち系の読みなら「サンファン」、「サンフアン」というあたりだろう。そしてこの都市は浮浪者街ではなくプエルトリコの首都である。
プエルトリコをやっていた人には、わかりやすいがわかりにくいゲームだ。
とりあえず、説明は簡単だ。「プエルトリコの、人と商品とお金が全部手札になったカードゲーム」といえばいい。
市長フェイズでカードを引き、商人でも採掘でもカードを引く。建設は、建設コスト分のカードを手札から捨てて行う。そういうゲームだ。
手札はすべて建物カード。船長フェイズはなく、建物の得点のみを競う。
で、プエルトリコを下敷きにしているがゲームはまったく違う。なにしろカードゲームだ。建てたい建物があっても引いていなければ建てられない。敵の手札がいいとどうしようもないことも多い。
しかし、プレイヤーの習熟度がそのまま勝率に関係しているのは確かだ。手札による勝ちパターンをいくつ知っているかで勝率が変わってくるゲームで、うまい人が必ず勝つゲームではない。ダメなときは誰がやってもダメである。

場の状況と手札を比べて進めていく感じはマジック・ザ・ギャザリングに似ていなくもない。プエルトリコよりも、プレイ感は『操り人形』に近い。
運が左右する部分が非常に大きく、プレイ時間も短めなのだが、気楽かというとどうだろう。なにしろ下敷きはプエルトリコである。それぞれのプレイヤーが役割カードを選び、それで発生したフェイズを全員がプレイする、という根幹は変わっていない。適当にプレイしていると他人に大きな迷惑がかかる。もっとも、慣れればそのあたりは簡単に判断できるようになるし、そこであえて違うものを選ぶといった楽しみもあるわけだが、慣れるまでは時間がかかる。
わたしの場合、もっぱら BrettspielWeltでプレイしているわけだが(まだ日本語版が発売されていない)、周囲の慣れているプレイヤーたちとやって、最初に10連敗した。ようやく得点の稼ぎ方がわかってくるとおもしろくなってきたという感じである。
BrettspielWeltでプレイしているわけだが(まだ日本語版が発売されていない)、周囲の慣れているプレイヤーたちとやって、最初に10連敗した。ようやく得点の稼ぎ方がわかってくるとおもしろくなってきたという感じである。
そのあたりもM:tGと同じだ。一度始めたら猿のようにやり続けなければ見えてこないゲームだと思う。M:tGをやっていた人なら誰でも経験があるだろうが、同じ相手と一晩徹夜してやり続ける、そういう遊び方が要求されている気がする。
買うのはプエルトリコを知っている連中だろうのに、これはまったく違うタイプのゲームだ。まあ、やり込みが必要という点は同じなのだが、戦略と駆け引きのみで運を必要としなかったプエルトリコのファンには、この運ゲーっぷりは受け入れがたいものがあるかもしれない。そのあたりは評価を落とす要因となるかもしれないが、しかし、別のゲームだと思えばこれはおもしろいと思う。
エレガントなゲームではなく、ルールが生みだす美しいカオスを堪能するタイプの(ライフゲーム型とでもいうか)「いいゲーム」とはいえない。そのあたりはプエルトリコから引き継がれた部分だ。多種多様な展開が生まれるが、それはルールが複雑だからなのである。そういうのが苦手な人もいると思うが、だがこれはこれで一つの形だろう。なんとなく「シンプル・イズ・ベスト」がテーゼとなっていた感のあるボドゲ界にあって、プエルトリコ、サンファンのヒットはちょっと小気味いいような気もする。
 プレイチャート
プレイチャート

操り人形
ボードゲーム
HANS IM GLÜCK
Bruno Faidutti
2-7人(最適5人・3人)
人数×30分
かなり売れているゲーム。カタンの次くらいに見かける頻度が高いんじゃないだろうか。2000円と安く、しかも確かにおもしろい。ドイツゲーム大賞にもノミネートされ、「カードゲームとしては10年に一度の傑作」とかいわれているらしい。売れている要因はそんなところだろう。
余談だが、ゲーム賞というのは、ノミネートさえされればもう評価を受けたと判断すべきものだ。大賞を獲ったゲームが一番おもしろいわけではない。おもしろさ以外にもさまざまな基準を持っているのが普通だから。むしろ、大賞を獲ってしまうのは欠点が少なく完成度の高いゲームであって、その分突き抜けたところがない。真に可能性を持った未来のゲームが欲しければ、大賞作品よりもノミネート上位作品を選ぶべきだと思っている。
さて、2000年のドイツゲーム賞から今まで売れ続けているのだから、ロングセラーだ。もっとも私は日本の状況しか知らないけど、少なくとも日本では、いまだに飽きられることなくプレイし続けられているということの証左といえるかもしれない。
でも。
正直にいえば、よくもこんなゲームがと思う。私も好きなゲームだし、おもしろい、飽きない、というところに反対するわけではないんだが。
パーティーゲームを楽しくやっている会場で「操り人形をやろう」とはいい出しづらいものがあると思う。

まあざっと紹介する。
国王プレイヤーから順番に、そのラウンドで自分が演じるキャラクターカードをとっていく。このとき、カードを他人には見せず、自分だけが見て一枚選ぶ。そして左隣のプレイヤーに、残りのキャラクターカードを渡す。そうやって、全員が一枚ずつの役割カードをとる。
マジック・ザ・ギャザリングのドラフトの要領、といえば知っている人にはわかりやすい。というより、間違いなくマジックの影響を受けたゲームデザインだろう。
次に、国王が順番にキャラクターを呼んでいく。呼ばれた人はここで初めて自分のキャラクターを明かし、手番をプレイする。
手番には、金貨を使って建物を建てる。より高価な建物をよりたくさん建てることのできたプレイヤーが勝者となる。
重要なのはキャラクターがそれぞれ持っている特殊能力だ。面倒くさいから全部紹介してしまおう。
暗殺者 ・キャラクターを一人指定して暗殺する。暗殺されるとこのラウンドは手番がなくなってしまう。
泥棒 ・キャラクターを一人指定し、そのプレイヤーから金貨をすべて奪う。
魔法使い・手札全部を他人と交換する。
国王 ・王冠カードをもらえる(これを持っている人が最初にキャラクターカードを選ぶ)
伝道師 ・傭兵の攻撃を受けない。
商人 ・金貨が追加でもらえる。
建築家 ・追加で建物カードをもらえる。その上、普通は1ターンに一枚の建物しか建てられないのだが、建築家は3枚建てられる。
傭兵 ・他人の建物を壊す。
くわしいルールをここに書いてもしかたないので端折ったが、これでもかなりめちゃくちゃなことが起こるだろうことはわかると思う。
特に暗殺者。暗殺を喰らうと、本当に大ダメージだ。なにもできないというのは、相当に不愉快でもある。
めちゃくちゃなことがプレイヤーの選択で起こせる、ということは、それだけ、他人に迷惑をかけなけらばならないゲームだということである。自分の得点を効率よく伸ばしていくだけのゲームではない。他人の戦略と複雑に絡まり合いながら、その中で自分が勝利を目指さなければならないわけである。
そこが、疑問なのだ。
私はこういうゲームは好きだ。しかし、初心者(あまり使うべき言葉ではないが)に対する敷居は高いんじゃないかと思っていた。
他人を無条件で一回休みにしてしまう暗殺者のために、場合によっては、2回も3回も手番を飛ばされてしまう。最初にやったゲームでそんなのを喰らったら、普通なら嫌になるんじゃないか。
他にも、傭兵や魔法使いなどで、不愉快なことがたくさん起こる。
それなのに売れている。不思議なのだ。(まあ「ドラフティングの楽しさを知っているマジックプレイヤーにうけている」というもっともらしい仮説は立てられるけど)
まだ戦略を考えるところにいきついていないプレイヤーとやるのは疲れる。
「初心者とやりたくない」とはいうべきでないし、そういうときは経験者が初心者をフォローすることを考えなければならない。これは初心者を勝たせるという意味ではない。プレイヤー間の関係が強いゲームだと、初心者のミスでゲームが壊れてしまう。ゲームが壊れるというのは、誰かが不条理に勝ってしまうとか単なる運勝負になってしまうとかそういうことだが、経験者はこれを防ぐプレイを心がけないと、せっかくの経験を生かして勝ちを目指すことができなくなってしまう。
で、そういうことを考えながらゲームをやっていると、どうなるか。
キャラクター選択の時に暗殺者が回ってきたら、必ずとらなければならなくなるのである。
暗殺者は他人に最も大きな影響を与えてしまう選択だ。しかしこれがいないとトップをとめられない。もう経験者が引き受けなければしょうがないじゃないか。
これはつらい。なにしろ相手プレイヤーを強烈に邪魔してしまう、悪役なのだ。しかも自分は他のキャラクターほど伸びない。
もちろん、そういうところも楽しむのがボードゲーマー。ボードゲーマーはマゾなのだが。
しかし、こんなつらくて不愉快なゲームが、よくもこんなに売れてるもんだなあと思ってしまうのである。世の中そんなにマゾヒストばっかりでもないだろう。やっぱり、マジックプレイヤーはたくさんいるということなんだろうか。
ってそんなことを書いたけど、間違いなくおもしろいゲームなのは確かです。おすすめ。
 カウンティング用建物データとか
カウンティング用建物データとか
A4ヨコで印刷してください。
数えてみたくなるのが人情というもの。それだけ。

フィレンツェの匠
ボードゲーム
Alea
R.Ulrich, W.Kramer
3-5人(3・4人)
90分
好きなゲームデザイナーは?
そう訊かれたら、「ウォルフガング・クラマー」と答える。だがそれは少し違う。順序が逆なのだ。このゲームおもしろいなーと思って調べるとデザイナーがクラマー、ということが非常に多いのである。
フィレンツェの匠もそうだった。クラマーらしいゲームではないのだが、デザイナーを知らずにプレイしておもしろいと思った。
この人は本当にいろいろなゲームを作る。しかし、すべてに通底する精神はある。できるかぎり例外的なルールを作らないこと、そして常に新しいゲームをデザインすることだ。
ゲームデザイナーであると同時に、この人は芸術家なのだろうと思う。だからハズレも多いのだが、細かいゲームバランスよりもゲームの展開それ自体のおもしろさの方を重視しているように思う。そういうところが、わたしは好きなのだ。
そんなクラマーの、芸術家をテーマにしたゲームである。
ルネサンス華やかなりしころ。フィレンツェの金持ちが、芸術家を雇って作品を発表させ、名声を得ていくゲームである。
いかにも金持ちらしく、芸術家のために自分の土地に建物を建ててみたり、公園を作ってみたりしていく。今でいえば、サッカーで話題のアブラモビッチみたいなものか。しかしこのゲーム、そういう豪快な雰囲気を味わえるかといえばそうでもなく、やはりクラマーのゲームらしく、高度な戦略と計画性を要求され、むしろ最低単位のお金を出すか出すまいか考える、しみったれたプレイを要求される。
ラウンド開始時には競りフェイズがあり、ここで各プレイヤー一つずつ、いろいろな効果を持つものを競り落とす。
次に各プレイヤーのターン。ここでは「作品発表」「建築」などの行動を2回おこなう。そして7ラウンドが終了したらゲーム終了である。
つまり、21回ある行動でいかに他人より多くの名声ポイントを獲得するかというゲームになる。
他人との関わりという部分がほぼ競りにしかないため、始めから7ターン分の計画を立ててゲームに挑むことが、できてしまう。慣れたプレイヤーになるといくつかの勝利手順を持っており、1ラウンド目のオークションの結果次第で方針を決定する。逆にいえばそれを持っていないプレイヤーは絶対に勝つことができないわけで、そこは欠点ともいえるが、おもしろいところでもある。
そして、慣れたプレイヤー同士ならば、けっきょく勝負を決めるのは落札価格ということになる。安い買い物をしたプレイヤーが有利になるのである。ゲームの局面を金額に換算する冷静な判断力が必要なゲームということになるだろうか。
余談だが、まあ、ここ数年の競りゲーブームにはちと食傷気味ではある。競りゲーというのはプレイヤーが競りの価格を決めていくため、デザイナーにとってはバランスの調整をする必要がなく、ずるいと思う。しかしまったく同じ理由で、やはり競りが入っているゲームはおもしろいものが多い。ただどんなに軽いゲームでも、競りが入ると非常に疲れる。
さてこのゲーム。クラマーらしいと思うところは、カードの引き方だ。
カードには3種類ほどあるのだが、引き方がどれも同じで、「山の上から5枚見て、うち1枚を引き、残りを山札の下に戻す」というものになっている。下に戻すのである。しかも山札はそれぞれ十数枚しかないので、ほぼ必ず一周する。つまりこれを憶えておけば有利になる場合があり、実際、建築をしまくる作戦(まあそういうものがあるのだ)の場合は山札をコントロールする必要があったりもするのだ。カードドローには運が必要だが、それをプレイヤーの腕で解消する手段も用意されているわけである。
やると疲れる、じっくりとり組むべきゲームである。だが、なにしろうまくいけば、始めに自分が立てた作戦どおりに事が運ぶわけで、勝利したときの充実感は大きい。その作戦と棋譜それ自体が一つの作品として発表されたかのような。なるほど、「フィレンツェの匠」とは(原題はだいぶ違うのだが)雇われた芸術家ではなく、プレイヤーたちのことなのではないかとも思える。

サンクトペテルブルグ
ボードゲーム
HANS IM GLÜCK
Michael Tummelhofer
2〜4人(4人)
1時間
職人と貴族を雇い、建物を建てて名誉点を稼ぐゲーム。といったって少しの説明にもならない。この説明があてはまるゲームが多すぎる。
だからシステムを説明しなきゃならないわけである。
各ラウンドには4つのフェイズがある。といっても各プレイヤーのターンにできることはまったく同じなのがおもしろいところだ。
まず第1フェイズは職人フェイズ。開始時に、場に職人カードがめくられる。
この場というのはいろいろなカードが出てくるのだが、必ずそれらの合計が8枚になるようにめくられる。前のフェイズで穴が空いた場所が埋められるわけである。
で、各プレイヤーのターン。できることは、
1)場に出ているカードを買い、自分の前に置く(職人フェイズだからといって職人しか買えないわけではない)
2)コストを支払わず場のカードを一枚手札にする
3)手札のカードを一枚、コストを払って自分の前に置く
4)パス
の4つ。全員がパスしたらそのフェイズは終了。
で、フェイズの得点計算と収入。各カードに、金の収入と名誉点が書かれており、職人フェイズでは職人カードに書かれた収入と得点の合計が入る。
職人フェイズが終わると、同様に、建築物フェイズ、貴族フェイズ、交換フェイズ(場のカードがポケモン風に進化するカードがめくられる)とおこなっていく。最後の交換フェイズだけは収入も得点もない。
つまり、各フェイズの違いは、始めにめくられるカードと、収入、得点が入るカードの種類である。できることに違いはないのだ。そのため、思っていたよりはぜんぜん簡単で、テンポのいいゲームになっている。
フェイズの手番順は持ち回りになっており、不公平感もない。
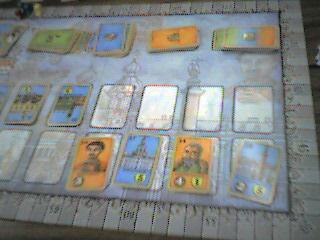
むろん3種類の収入、得点源は差別化されている。職人は基本的に金だけ。貴族は職人より効率が悪いが金と、高価なものでは得点も入る。建築物では高い得点が入る。
こういうゲームではいかにもありそうな、特殊効果を持つカードというのもある。
で、4つの山のどれかが尽きたラウンドでゲーム終了。最後に、持っている貴族カードの種類に応じて(1+2+……+n点)得点が加算される。
要は、基本的には拡大再生産していくと考えていい。のだが、そのバランスが微妙で、そこもおもしろいところだ。効率の悪いカードでは投資金を回収できそうもないものもあるし、序盤に考えずにやっていると手詰まりになりかねないのである。
さて、ルールを説明したところで、不満がある。これは完全にカードゲームなのである。それなのになぜボードと駒がついてくるか。定価は4000円と安いのだが、カードゲームだと思うと高いのである。まあ、ゲームがおもしろいからいいけど。
とりあえず、いろいろ作戦を考えたくなるわけである。職人作戦とか貴族作戦とか、特殊カード作戦とか。まあ実のところ、完全にどれかを切り捨てて勝てるとは思えないわけだが、どこかに重点を置くことは可能だ。
そうして収入と得点のバランスを考えながら勝利形を捜していくプレイ感覚は、意外だがサン・ファンに近い。最近のトレンドなのだろう。だがずっとシンプルで、経験者と初心者との間の格差もサン・ファンほど大きくはない。
プレイ時間も、まあ考える気になれば考えてしまえる部分はたくさんあるが、それでも思ったほどにはならない。
いいゲームである。わたしが今もっとやりたいゲームナンバーワンだ。だが「サンクトペテルブルグやりましょう!」というと舌を噛みそうなのが一番の不満である。
 カードリスト
カードリスト
A4ヨコで印刷してください。
やはりね、知ってると知らないとではずいぶん違うから。
建物の名前とかはいろいろ呼び方があるようだけど、訳は原意とメビウス訳を尊重してみた(つもり)。
 PC版サンクトペテルブルグ
PC版サンクトペテルブルグ
コンピュータ3人と対戦できるソフト。むろんわたしが作ったわけではなく、Westpark Gamersというサイトで公開されているもの。コツを掴んだプレイヤーくらいの強さはあるので、練習(ヒマつぶし)にはいい。

キャストエニグマ
ボードゲーム
株式会社ハナヤマ
Eldon Vaughn・芦ヶ原伸之
1人
4時間〜数日
ごめん。ちょっと自慢したかっただけ。
ちょっと前から静かなブームらしいキャストパズルの最新作で、「難易度は史上最高」と派手に宣伝しているもの。なにしろ、外したところを写真にとってメーカーに送ると特製キャストパズル用巾着袋がもらえるというキャンペーンまでやっている。

ちなみに、写真に映っているのがその巾着袋である。
普通、この手の知恵の輪というのは、「とれそうでとれない」からがんばりたくなるものだが、エニグマは違う。いいかどうかはともかく、そこがこのパズルのもっとも特徴的なところだ。
一見、とてもとれそうじゃないんである。まずしばらくいじってみて、たいていの人の感想が「不可能」。この絶望感はちょっと感じたことのないものだった。
しばらくいじっているとだんだんとできることがわかってくる、この点は他の知恵の輪と同じ。しかしエニグマは、できることが多すぎる上に、解法に近づいているのかどうかがまったく判然としない。最後の最後まで、「ほんとにこれでいいのか?」ともう一度最初からやり直したくさせる。
キャンペーンをやって煽ったのは、そういう意図もあったんじゃないかと勘ぐりたくなる。始めから不可能と感じる知恵の輪は、時間を消費する娯楽としては、あまりいいことじゃないような気がするのだ。
だだっ広い平原のど真ん中で始まるロールプレイングゲームのようなものである。どうしていいかわからないまま歩いてみなければならない。
だからまあ、エレガントな解法に気づいて「そうだったのか!」というような、真犯人がわかったときのカタルシスのようなものは薄い。
同じキャストパズルのシリーズでいえば、キャストデビルとかキャストホース、キャストニューズみたいな、名作かもしれないパズルとは違う。そういうパズルをすべて解いてしまったあとで、パズル中毒になってしまった人がやるパズルだと思う。ファミコンのクソゲー『たけしの挑戦状』みたいなもんだろうか。あんなにひどくはないが。
 株式会社ハナヤマ
株式会社ハナヤマ

